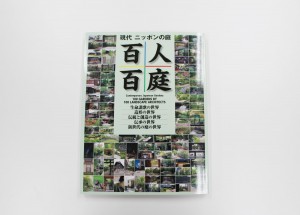建築の力

ご相談いただいております計画の現地調査でのこと。
なんと、敷地にある建物は明治43年に建てられた、築105年も経過したもの。
この老朽化した建物を「残すか」「建て替えるか」の判断材料を集めるための現地調査だったわけですが
立ち会ってくださった、近くに住む建主さんのおばあさまが、
建物のことを色々と教えてくださいました。
当時この建物がいかに立派であったかということ、
おばあさまのお姑さんから棟梁について聞かされていたこと、
変わりゆく町の中でどのようにして残り続けたかということ。
この建築を大切に思う気持ちが伝わってきました。
「残すか」「建て替えるか」の結論は
今後、耐震面・性能面・現代の生活との擦り合わせ・経済面など
多方面からの検討が必要で、慎重に冷静に進めていく必要があります。
ただ、おばあさまのお話を伺って改めて思うのは
建築の力と、それに関わる身としての責任。
100年を超えて尚、愛される対象になりうる存在であるということ。
今新たにつくられる建築も、全ていつかは古いものになっていきます。
時代やライフスタイルは変わっていけども、変わらないのは建築は常に人と共にあるということ。
目先の便利さや機能性という言葉の先にある、
建築と人との幸せな関係を築くことを目標に、やっていこうと思います。
keep smiling!
奥野 崇
椅子の愉しみ

事務所の打ち合わせ用の椅子に
ウェグナーのCH33が新たに仲間入り。
1957年にデザインされたものですが、その姿に古くさい感じは全くしません。
また、非常に軽く動かしやすく、肘も少し掛ける事ができます。
アームが無い分、テーブルにすっきり収める事ができるのもいいところ。
体が直接触れる家具は、生活する中でとても大切な存在。
表面的な綺麗さだけでなく、
ライフスタイルにあった丈夫なものをチョイスしたいものです。
私は、住まいを考える中で
建築と同じくらい家具の選択は重要なものと考えています。
そのため、事務所にはそれらの家具を実際に体験・取り扱いできる環境を整えています。

次なる仲間入り予定はPPモブラーの68。待ち遠しい!
keep smiling!
奥野 崇
あけましておめでとうございます
あけましておめでとうございます。
気温の低い、風の強い一日での幕開けとなりました。
毎日を大切に、積み重ねていこうと思います。
本年もどうぞ宜しくお願い致します。
keep smiling!
奥野 崇
今年の最後

2014年最後のメールの送信を終えました。
思えば、あっという間の一年。
おかげさまで特に、新しい出会いの多い年となりました。
来年はその出会いがカタチになっていく年となりそうです。
なんとも楽しみ。
年明け早々からは、新しいメンバーも加わります。
事務所の体制ももう少し整えて、学びの蓄積を大切にしていきたいところ。
素直に、強く。
皆様、どうぞ良いお年をお迎え下さいませ。
keep smiling!
奥野 崇
このところ。
今月発売されました「百人百庭」に
建築設計を致しました、
長浜の家が掲載されています。
本誌は庭の専門誌で
作庭してくださった仙波太郎さんの仕事が紹介されています。
「庭の価値観を理解した建築家と
真摯な姿勢で庭に関わる作庭家との稀なる出会い」〜本文より
とご紹介くださいました。
日頃より、内部空間としての建築と、
外部空間としての庭との関係を大切にしながら設計をしようと考えていましたから、嬉しいお言葉です。
このところ全国の庭に関わる方々との交流がふえてきて思うのは
きっと、ひとつひとつの仕事に悩み、試み、また学びながら大切にされてきた結果であろうと。
そのものの本来の姿以上に、よくみせかける事が横行する今。
建築の世界も同じ。
現代とこれからの社会の「本当」をつくる上で
建築設計を受け持つ私たちの責任は大きい。
keep smiling!
奥野 崇
河原学園さんでの講演にて

河原デザインアート専門学校の学生のみなさんに
住宅設計について、これからの働き方について
お話しさせていただきました。
講演、は普段の仕事や感じていることを、俯瞰し言語化するいい機会だなあ、と。
質疑応答の時間には、核心をついたものもあり
私のほうが本当に学ばせて頂きました。
ありがたいこと、です。
河原学園の富久さん、中村さん、津口さん。
ありがとうございました。
keep smiling!
奥野 崇
人と言葉との出会い
週末は催しが続きました。
22日土曜は共栄木材さん主催の木造建築講演会へ。
竹原義二さんと中村好文さんの講演、対談の会です。
内容はもちろんですが
歌うように話される中村さんと、たたみ掛けるように話される竹原さんの姿が
お二方をあらわしているようで、とても印象的。

実は、中村さんとは
notesに収録しております昨年のアマンダリでの滞在時に
ばったりお会いしていたのでした! ※赤ちゃんはうちの子供です
23日日曜は、
庭園協会主催のシンポジウム「庭と建築を考える」に参加するため
今治、朝倉にある創造園さんへと。
創造園さんは、初めてお邪魔させていただきましたが、
敷地内に点在する石の水の彫刻には無意識にも目が止まります。
その荒々しい表面とは別に、全体からは「優しさ」や「繊細さ」を感じます。


淡路の左官職人の久住章さんや、姫路の造園家の大北望さん、
もちろん創造園の越智さんらも参加されたこの会。
「左官を通じて、生きる喜びをつくりだしたい」とは久住さんの言葉。
越智さんとの最後にお話しの中から、
「自分の目でひとつひとつ確かめながらやってきた。今も新しい試みをやっている」とのこと。
今をもってなお、前進しようとする姿がとても印象的。


また、素敵な方々と忘れられない言葉達と出会えました。
私たちも、もっといい仕事をしよう。
Keep smiling!
奥野 崇
スケッチ

設計を進めるにあたり、奥野事務所ではスケッチを重要視しています。
空間のプロポーション、素材などを
描きながら検討するのが一つの方法になっています。
そのまま打ち合わせにも使用しますし、
スタッフとの意思疎通のツールとしても重宝します。
このスケッチは、現在実施設計中のお住まい。
松山市内にて来年中旬の竣工を予定しています。
Keep smiling!
奥野 崇
高校生への講演

22日に高校生にむけて講演をしました。
県立松山工業高校建築科の皆さんにむけて、です。
この取り組みは「次世代を担う地域産業育成事業における匠の技教室」というのが正式な呼称。
地域の企業への理解を深め、地域企業で活躍できる人材の育成を図る、というのが学校から頂いた目的でしたが、講演の後半では
世界の高校生世代がどのような活躍をしているか、ネットの活用による仕事の仕方の変化など
これからの時代の働きかたの展望についてお話しさせて頂きました。
物事がどんどん変化する時代。
技術やテクノロジーはどんどん進化しますが
その仕事の中心には、「人を幸せにすること」を忘れないで活躍していってほしいものです。
keep smiling!
奥野 崇
木の建築賞 公開プレゼン

去る10月11日に、山口県の宇部にて行われた
木の建築賞の公開プレゼンテーションにいってきました。
以前のブログ でも紹介しましたとおり
60を超える応募の中から「長浜の家」が上位20選に選ばれたためです。

諸先生に囲まれてのプレゼンで
「緊張してます」の第一声ではじめた私の時間でしたが
木造建築へのまなざし、
住まいを設計する際の決め事、
住まいづくり=繋がりづくり、といった自分の想いを説明させて頂きました。
質疑応答の際には委員の先生から
素材の選定、使い方、
全体のバランスや完成度について、お褒めの言葉を頂きまして、
一次選考会では各作品の設計者名を伏せての審査であり、
「長浜の家」は老練な設計者を想像していたのだけれど、、、
とのエピソードも聞かせて下さいました。
帰りの便の関係で最後まで会場にいることができず
委員の先生皆様とゆっくりお話しできませんでしたが
横内敏人さん三澤文子さんから、
「続けていればまた会えますよ」と言って頂き、
自分の仕事は全国に繋がっているんだなと実感。
これからも四国を中心にしっかりと、
木の建築の更なる高みを目指していこうと、強く想うのでした。
keep smiling!
奥野 崇
第10回木の建築賞
| 選考委員長 | |
| 泉幸甫 | 泉幸甫建築研究所・日本大学 教授 |
| 選考委員 | |
| 安藤邦廣 | 里山建築研究所 主宰・筑波大学 名誉教授 |
| 池田昌弘 | (株)Masahiro Ikeda School of Architecture 主宰 |
| 杉本洋文 | (株)計画・環境建築代表取締役・東海大学 教授 |
| 中谷正人 | 中谷ネットワークス 主宰・千葉大学 非常勤講師・千葉大学 特任研究員 |
| 速水亨 | 速水林業代表・(社)日本林業経営者協会 顧問 |
| 播繁 | 播設計室 代表 |
| 松井郁夫 | (株)松井郁夫建築設計事務所 所長 |
| 三澤文子 | MSD代表・京都造形芸術大学通信大学院 教授 |
| 南雄三 | 住宅技術 評論家 |
| 安井昇 | 桜設計集団一級建築士事務 代表 |
| 横内敏人 | (有)横内敏人建築設計事務所所長・京都造形芸術大学 教授 |
| 客員選考委員 | |
| 内田文雄 | 株式会社龍環境計画代表・山口大学大学院 教授 |
| 金子敦子 | 金子工務店 専務取締役・山口芸術短期大学 非常勤講師 |