八月の喫茶開店日について

自分たちの想う”いい”を集めてみる。
茶|菓子|器|古物|音景|空間
8月の喫茶開店日のお知らせです。
市内から車で20分のショートトリップ。
夏の終わりの良き一日となりますように。
[日程]
8月25日(日)
10:00~15:00(LO14:30)
詳しくは、
喫茶 穀雨
奥野崇 建築設計事務所
高松の家

今年の初めに竣工した、高松の家を訪ねました。
お茶に縁のあるご家族の住まいです。
造園工事も落ち着いて、一段落。
夏の終わりころの撮影となりましょうか。
奥野 崇
七月の開店日について

月に一度、日曜だけ開店する喫茶をはじめて一年。
少しずつ、ですが
私たちなりのお迎えができるようになってきた気がしています。
七月の席は、ほんの少しチャレンジを。
これまでのような完全予約制の二時間コースではなく
予約なしのご来店も可能な
ちょっとカジュアルな一日にしてみようと思います。
市内から車で20分のショートトリップ。
良き夏の一日となりますように。
[日程]
7月14日(日)
10:00~15:00(LO14:30)
[駐車場について]
5台分あります。
できるだけ乗りあわせでお願いします。
車がいっぱいのときは、入店頂けない場合もあります。
詳しくは、
喫茶 穀雨
奥野崇 建築設計事務所
半化粧(ハンゲショウ)

「半化粧」の名は、
葉の半分ほどに真っ白な胡粉を塗ったような様子から、そう名付けられたそうです。
また、夏至から数えて11日目を半夏生と呼び、
そのころに花を付けることから「半夏生」の異名もあります。
いまはちょうど夏至の頃。
今年は少し早い花付きとなりました。
梅雨の合間の日差しのもと
気持ちよさそうに、ころころ揺れています。
奥野 崇
住宅医と日本茶と

ライフロングラーニングとはいったもので、
いくつになっても学び知ること、深めていくことは愉しいものです。
建築に関係するものはもちろん、それ以外のものもそう。
今年は通常の設計業務と並行して、ふたつの検定修了を目指しています。
ひとつめは、住宅医。
かねてより、既存建物の利活用についてとても関心がありました。
住宅医は、大阪の三澤文子さんを発起人として
既存住宅のリノベーションに纏わる
診断や改修手法、耐震や温熱計算はもちろん
木材腐朽のメカニズムや、福祉領域から見たバリアフリー設計まで、改修工事に特化した知見を学ぶものです。
築後、時を経た建物を知ることは、
新築の設計を行うときにもそれはそれは役に立ちます。
デザインの名のもとに、それらしく取り繕ったものは、
時の流れの中、自然の摂理によってしっかり答えがでてきますから。
ふたつめは、日本茶インストラクター。
茶道に縁があったこともあり、
日本茶全般にはとても興味を持ってきました。
茶の歴史や製法、煎茶の作法まで学習してみようと思っています。
海外の方々と関わることも増えてきたこの頃。
自分のルーツである日本のことを学ぶということは、とても大切なことだと思います。
奥野 崇
touten 1

静かになった夜のアトリエ。
GENEVAのスピーカーで音楽を流します。
touten 1 / 江﨑文武 (2022年)
ミュートしたアップライトピアノによる即興演奏を、奈良のlistudeで収録したものです。
里山の環境音とよく馴染む、繊細な抑揚表現にやわらかい音色。
時間の背景となるような、控えめな音楽が好きです。
奥野 崇
御礼
 蛍の席、
ご参加頂きました皆様と
たくさんの蛍たちのお陰で
思い出深い、ひとときとなりました。
ありがとうございました。
夜の里山散歩。
星空の下、ひんやりした空気と、蛙や虫の声、川の音。
私達のほうこそ満たされておりますとも。
夏以降、規模の大きな物件の着工が続きます。
また喫茶のほうも、新たな展開をと思案しております。
設計も喫茶も、
どうぞご期待くださいませ。
奥野崇 建築設計事務所
喫茶 穀雨
蛍の席、
ご参加頂きました皆様と
たくさんの蛍たちのお陰で
思い出深い、ひとときとなりました。
ありがとうございました。
夜の里山散歩。
星空の下、ひんやりした空気と、蛙や虫の声、川の音。
私達のほうこそ満たされておりますとも。
夏以降、規模の大きな物件の着工が続きます。
また喫茶のほうも、新たな展開をと思案しております。
設計も喫茶も、
どうぞご期待くださいませ。
奥野崇 建築設計事務所
喫茶 穀雨


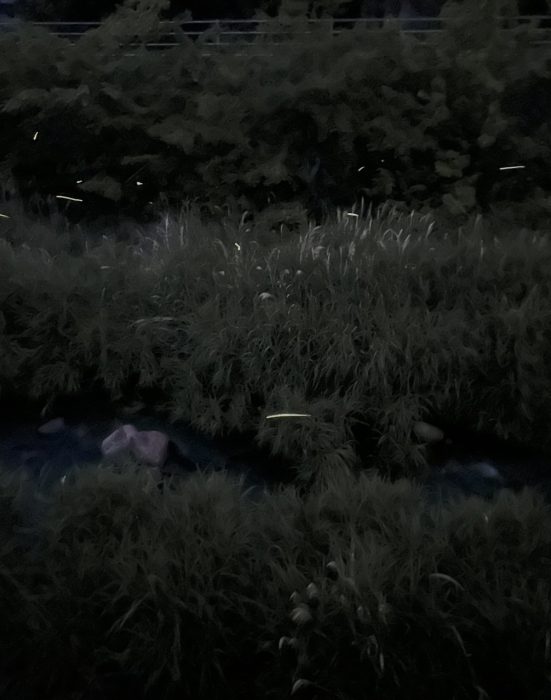 蛍の席、
ご参加頂きました皆様と
たくさんの蛍たちのお陰で
思い出深い、ひとときとなりました。
ありがとうございました。
夜の里山散歩。
星空の下、ひんやりした空気と、蛙や虫の声、川の音。
私達のほうこそ満たされておりますとも。
夏以降、規模の大きな物件の着工が続きます。
また喫茶のほうも、新たな展開をと思案しております。
設計も喫茶も、
どうぞご期待くださいませ。
奥野崇 建築設計事務所
喫茶 穀雨
蛍の席、
ご参加頂きました皆様と
たくさんの蛍たちのお陰で
思い出深い、ひとときとなりました。
ありがとうございました。
夜の里山散歩。
星空の下、ひんやりした空気と、蛙や虫の声、川の音。
私達のほうこそ満たされておりますとも。
夏以降、規模の大きな物件の着工が続きます。
また喫茶のほうも、新たな展開をと思案しております。
設計も喫茶も、
どうぞご期待くださいませ。
奥野崇 建築設計事務所
喫茶 穀雨