as it is
古道具坂田において
独自の審美眼で知られた
坂田和實さんの私設美術館。
最後の催しへとお邪魔してきました。
(九月をもって閉館されるとのこと)

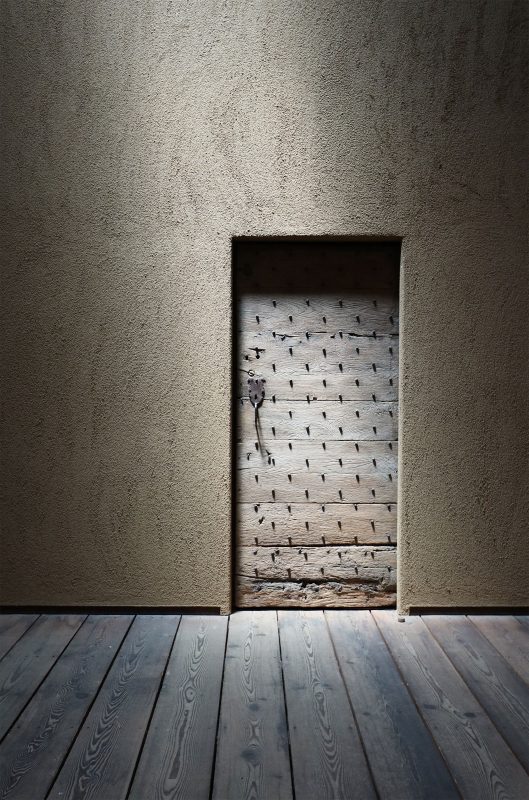

雨上がりのしっとりした朝。
as it is = 儘
という名のとおり、
変わらない閑かな空間と時間が、そこにはありました。
keep smiling!
奥野 崇
私たちの場所づくり、はじめます

松山市内から車で20分程。
辺りは人と自然が調和をなす里山地域。
出会いと縁が重なり、
築35年の建物をリノベーションして、
オフィス 兼 ギャラリーをつくり始めました。
ゆっくりじっくり、
来春の頃には、お披露目ができればいいな。
素晴らしい周辺環境のもと、
「暮らすように働く」をテーマに。
窪の離れ、とは
私たちの想う”いい”を実践・表現する場所です。
keep smiling!
奥野 崇
詳しくはInstagramで更新しています。
知恵と工夫

事前の準備、試作を重ねた上での現場入りは左官職人さん。
曲面にフィットする頑丈な型枠製作は大工さん。
知恵と工夫の賜物です。
鮨店の現場は、日曜も静かに進行中。
keep smiling!
奥野 崇
蝸牛(かたつむり)

でんでん虫、舞々、かたつむり、つぶりなど
多くの異名をもつ蝸牛。
古くから子供達に親しまれており
民俗学者である柳田國男は、
方言の好例として日本全国の呼び名を調査したほど。
梅雨の代名詞ともいえる存在。
孵化したばかりの、かわいらしい季節です
keep smiling!
奥野 崇
樹々の中で
名古屋・奈良での打合せにあわせて、
宇陀市の山間にある室生寺へ。

寺院が俗世から離れ、山林修行の場へと移行していく初期のものといわれています。

江戸時代に付加された手前一間の礼堂は
なんの違和感もなく一体に在ります。
都を離れ、山野に佇むその姿は
慎ましくも安心感に満ちています。
keep smiling!
奥野 崇
土の姿
「素材の声を聞きなさい」
とは、ルイス・カーンの言葉。

土という素材は、どうすれば心地よくあるのか。
手の付けかたによって、どんな表情をするのか。

湿り気を抱え込むその姿を追い求めています。
keep smiling!
奥野 崇
美意識の結晶
いつかのこと。
老舗漬物店が運営する宿泊施設です。
Bijuu
柳原照弘さんの美意識が具現化されたもの。
何度見直しても、見惚れる空間。








keep smiling!
奥野 崇
読点

先の週末のこと。
香川県は三野町にある寺院の起工式を終えました。
ここに至るには、三年の月日。
これも住職、総代、檀家の皆様をはじめ
多くの方々のご尽力に他なりません。
今回の工事では、
主に本堂の改修、護摩堂の改築を行い
ここから更に二年を越える工事となります。
とうとうと続く時間の流れ。
あらゆるものは、
何かが始まって、何かが終わるでもないのかもしれません。
今回のことも文中の切れ目に打つ読点のようなもの。
ながく育んできた地域の記憶を大切に
過去と今と未来とを繋げていくべく
しっかり努めて参ります。
keep smiling!
奥野 崇
海陽町からの贈り物
その表皮は、まるで自然の産物のよう。
夏の薫りが漂いはじめた頃、
池田優子さんからお茶碗と茶入が届きました。


池田優子さんは大阪在住の作陶家です。
昨年11月。
連絡頂いたことをきっかけに、
徳島県海陽町にて
新たに設ける窯作りのお手伝いを致しました。
海陽町での開窯記念に焼かれたものだそうで、
茶入れには、浜辺で見つけた貝殻が。
お茶碗も、どこか海の気配がするように感じます。
すっかり色濃くなった
夏の海陽町での再会がたのしみでなりません。
※12月4日からは
松山のSTOROLLさんにて個展の予定があるとのこと。
こちらもたのしみな催しです。
keep smiling!
奥野 崇
暮らしの器
竣工して、もうすぐ一年。
まあたらしくて、ガランとしていた空間から
すっかり人の住まいになっていました。
建物が前に出すぎることなく、
日々の暮らしをやさしく包み込むように。
晩春の空の下、今治の家にて。











keep smiling!
奥野 崇
